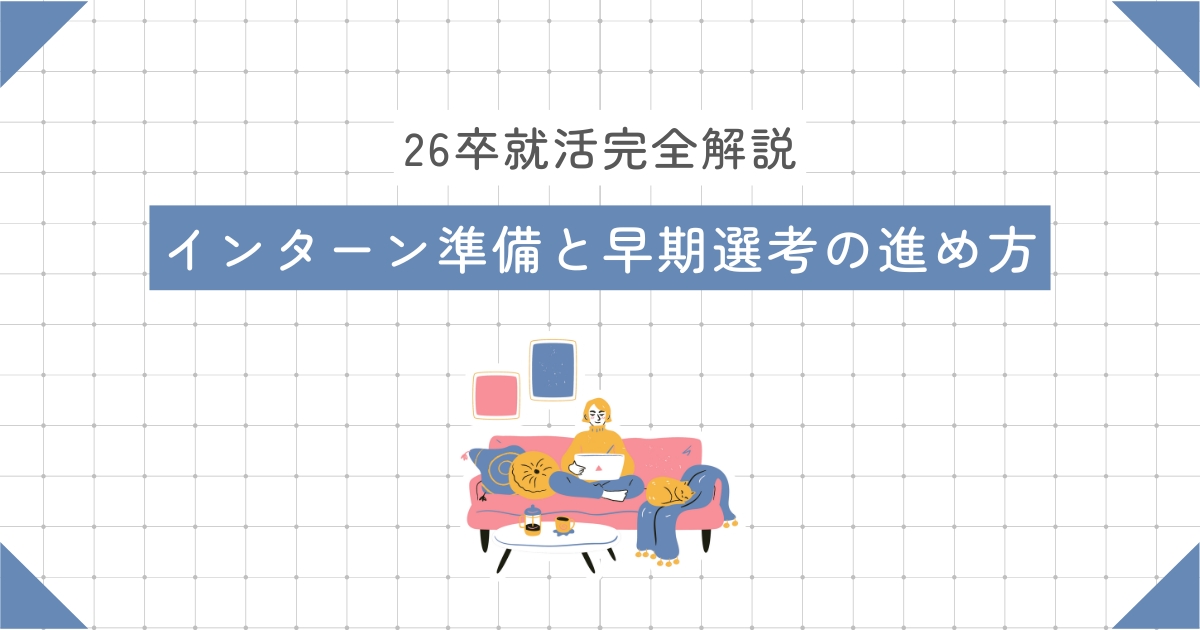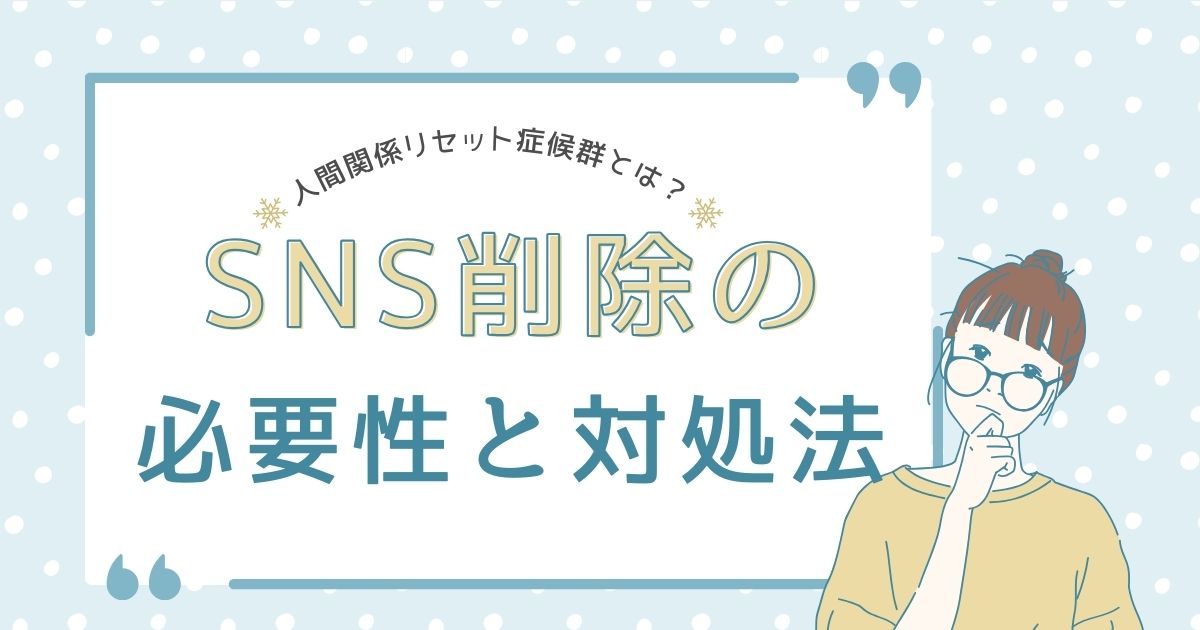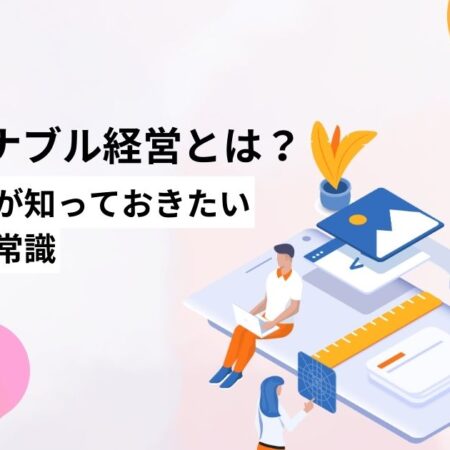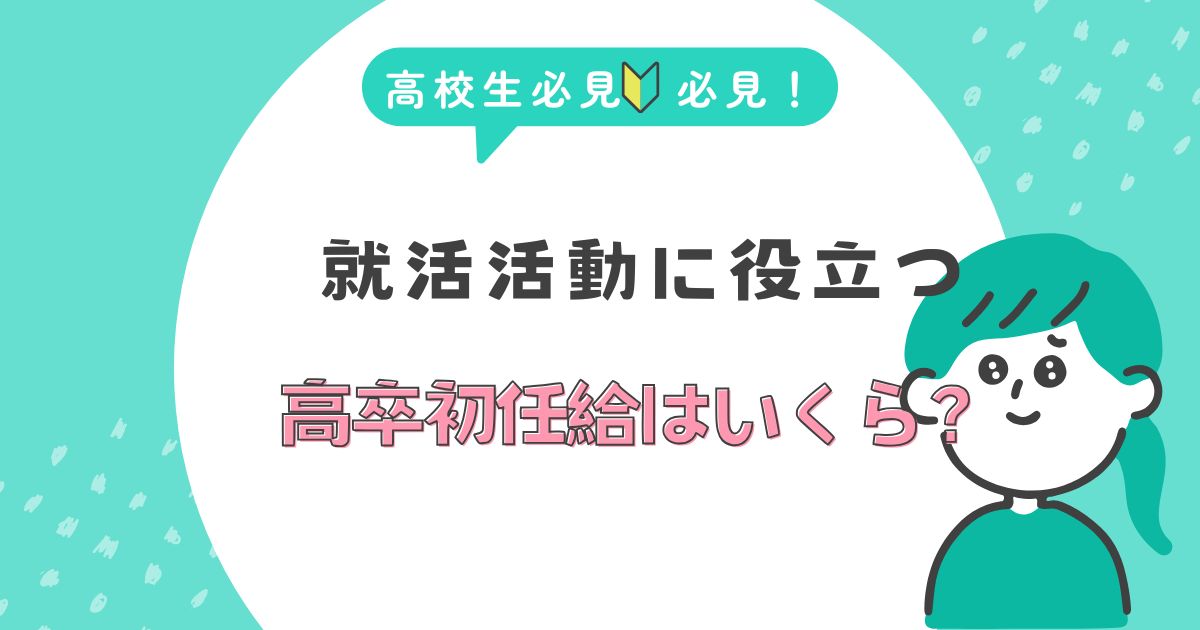「やさしい日本語」は、日本語話者以外に向けた言語配慮として始まりました。1995年の阪神淡路大震災を契機に注目され、情報伝達の手段としてやさしい表現を研究する流れが全国に広がりました。近年では、外国人住民だけでなく、Z世代の若手社員とのコミュニケーション改善にも役立つと注目されています。
本記事では、「やさしい日本語12のルール」をもとに、誰にでも伝わる言葉の使い方をわかりやすく紹介します。簡単な言葉・短い文・分かち書きなどの工夫が、社内外での情報発信や定着支援にどう活用できるのか。外国人にとっても、Z世代にとっても伝わる言葉とは何かを具体例とともに探っていきます。
外国人・Z世代が抱える伝わる壁とは?
企業の現場では、外国人社員やZ世代の若手社員とのコミュニケーションにギャップを感じているという声が少なくありません。とくに、日常的に使われている日本語が、日本語に不慣れな相手には複雑すぎることがあります。
例えば、敬語や婉曲表現、漢字の多用、抽象的な言い回しは、外国人にとってわかりにくいだけでなく、Z世代の若者にも伝わりづらいケースが見られます。彼らは、直感的でシンプルな伝え方を好む傾向が強く、曖昧な言葉や間接的な表現には戸惑いを感じるのです。
その結果、意思のズレや誤解が生じ、業務効率やモチベーションの低下を招く恐れがあります。こうした問題を回避するためにも、文を短く、簡単な言葉で、構造を明確にすることが求められます。

現場で実際に起きたコミュニケーションのすれ違い
ある企業で、若手社員が上司からの指示を理解できず、業務が進まないという問題が発生しました。上司は抽象的な表現を多用し、具体的な指示が不足していたため、部下は何をすればよいのか分からずに困惑していました。
指示の例
- 従来の指示:
- 「このプロジェクトを進めておいてください。」
- 改善後の指示(やさしい日本語)
- 「このプロジェクトのために、次のことをしてください。まず、資料を集めてください。次に、集めた資料を使って、レポートを作成してください。レポートは来週の金曜日までに提出してください。」
ポイント
- 具体性: 指示を具体的にすることで、部下が何をすればよいのか明確に理解できるようにしました。具体的な行動(資料を集める、レポートを作成する)を示すことで、部下は自分のタスクを把握しやすくなります。
- 期限の設定: いつまでに何をするのかを明確にすることで、部下は優先順位をつけやすくなります。これにより、業務の進行がスムーズになります。
- 確認の促し: 指示の後に「何か質問はありますか?」と尋ねることで、部下が不明点を確認しやすい環境を作ります。これにより、部下は自信を持って業務に取り組むことができます。
やさしい日本語を使った指示の具体例をいくつか挙げます。これらの例は、特に外国人や日本語を学ぶ人々にとって理解しやすいように工夫されています。
1. 災害時の指示
事例1:外国人社員が地震避難指示を理解できなかった
- 「避難場所へ速やかに移動してください」という表現が理解されず、安全確保が遅れた。
- 対応:「じしんです。にげてください。こうえんへ。」という簡単な日本語+分かち書きで改善。
やさしい日本語12の規則とは何か?
「やさしい日本語12のルール」は、日本語に不慣れな外国人や外国人住民、さらにはZ世代にも配慮した伝わる日本語の基本指針です。弘前大学人文学部 社会言語学研究室によって整理され、2020年1月時点で広く共有されていました。
この12のルールは、日本語話者以外の人にとって理解しやすくなるように設計されています。その背景には、1995年の阪神淡路大震災や東日本大震災の際、情報発信が伝わらず命に関わる事態が多く発生したことがあります。こうした経験から、文の構造をシンプルに、語彙を易しく、文を短くする必要性が社会的に認識され始めました。
やさしい日本語は「支援の手段」であり、情報伝達の手段でもあります。行政、企業、教育機関など、さまざまな場面で活用が進んでおり、今では日本人同士の意思疎通にも有効であることが明らかになっています。
一つひとつ丁寧に解説!使える日本語の具体例
以下に、やさしい日本語12のルールの一部と、実際に職場で使える例文を紹介します。
- 難しい言葉を避け、簡単な語彙を使う
✕ ご確認いただけますと幸いです
〇 見てください - 1文を短くする/短くして文を区切る
✕ この件について、社内で調整後、担当者が改めて連絡します
〇 このことは、あとで話します。担当の人から、れんらくします。 - 分かち書きを使う(単語ごとにスペースを入れる)
例:かいぎ は 3がつ5にち に あります。 - 漢字にはふりがなを付ける/使用量に注意
例:会議(かいぎ)、確認(かくにん) - 外来語を使用しない/代わりの日本語に置き換える
✕ コンセンサス → 〇 いけんが おなじ こと
✕ アポイント → 〇 よやく、やくそく - 文の構造をわかりやすくする/主語と述語をはっきりさせる
例:わたしは、かいぎに いきます。 - 動詞を名詞に変えない
✕ ご提出をお願いします
〇 出して ください - だけ動詞文(「する」「ある」「いる」などだけ)を避ける
✕ あります → 〇 なにが あるか いいます
このような表現にすることで、相手の理解度が大きく向上します。
加えて、ローマ字は使わないでください、後に< >で補足するなどの配慮も有効です。
やさしい日本語の活用で変わる社内コミュニケーション
やさしい日本語は、単なる支援ツールではありません。企業の現場で導入することで、社内コミュニケーションの質を劇的に改善する力を持っています。特に、外国人社員やZ世代の若手社員が混在する職場では、共通言語のような存在となり、円滑な業務遂行と人間関係構築に寄与します。
例えば、業務連絡や朝礼での発言、マニュアルの記述、社内メール、掲示物など、さまざまな場面で活用できます。
以下のようなポイントが重要です:
- 複雑な敬語や婉曲表現を避け、簡潔に伝える
- 文を短く、主語・目的語を明確にする
- 必要に応じて分かち書きやふりがなを付ける
- 漢字や外来語の使用量に注意する
こうした工夫は、外国人にとって理解しやすいだけでなく、Z世代にも安心感を与える結果につながります。つまり、「やさしい日本語」は多様性を活かす組織文化の土台にもなり得るのです。
職場の多様性に対応する言葉の工夫
では、実際に職場でどのように使えるのか。以下はケース別の活用例です。
◇社内メール
- ✕ ご査収のほどよろしくお願いいたします
- 〇 見てください。何かあれば教えてください。
◇朝礼や会議での話し方
- ✕ それぞれのプロジェクトに関し、速やかな対応をお願いいたします
- 〇 しごとは、すぐ してください。まにあうように がんばりましょう。
◇掲示物・ポスター
- ✕ 防災訓練は3月5日に実施予定です
- 〇 ぼうさいくんれん は 3がつ5にち に あります。
◇社内マニュアル
- ✕ このフォームに必要事項を記入のうえ、提出してください
- 〇 このかみに、かくこと を かいて、だして ください。
これらは一見すると「幼稚な表現」にも見えますが、実際には伝達の精度が向上し、誤解やトラブルを防ぐ効果があります。使う側の配慮こそが、職場全体の信頼関係をつくる第一歩なのです。
情報発信におけるやさしい日本語の効果とは?
やさしい日本語は、社内外の情報発信においても極めて効果的です。特に、外国人採用を積極的に進めている企業や、Z世代に親しみやすい企業文化を発信したい担当者にとっては、有効なブランディング手段となります。
自治体の広報活動や防災情報の発信でも活用されており、その効果は実証済みです。たとえば、2020年の地震情報や感染症対策の案内など、全国の自治体では「やさしい日本語」への翻訳が進められ、外国人住民の理解度向上に役立てられました。
また、企業の採用サイトやパンフレットにおいても、あえて「やさしい言葉」で表現することで、安心感や信頼感を訴求できます。これは、単に外国人向けだけではなく、若年層における情報処理ストレスの軽減にもつながるのです。
採用サイトや社内文書における実践例
以下に、実際の情報発信シーンで「やさしい日本語」がどのように使われているかを示します。
◇採用サイト(外国人向けページ)
- ✕ 弊社はグローバル人材の積極採用を推進しています
- 〇 わたしたちのかいしゃは、外国の人を たくさん むかえたいと おもっています。
◇入社手続きガイド
- ✕ 必要書類をご確認の上、期日までにご提出ください
- 〇 たいせつな かみ を みてください。まえもって だしてください。
◇社内掲示(感染症対策)
- ✕ 出社時は体温測定およびマスクの着用を徹底してください
- 〇 かいしゃに くるときは、ねつを はかって ください。マスクを つけてください。
◇社内報・イントラネット
- ✕ 社員の声をもとに、社内制度の改善を進めています
- 〇 みんなの こえ を きいて、かいしゃの ルール を よくして います。
このように、「やさしい日本語」を用いることで、相手にストレートに届く情報発信が可能になります。特に、多様な背景を持つ人々に対して、“伝わる”文章を作るという視点は、これからの企業に必須の感覚です。
若手の定着率を高めるためのやさしい日本語戦略
人材の定着は、あらゆる企業にとって重要なテーマです。特にZ世代の若手社員は、対話やフィードバックに敏感であり、共感やわかりやすさを重視する傾向があります。こうした世代にとって、「やさしい日本語」を使ったコミュニケーションは、単なる言語表現ではなく、安心感を与える文化的メッセージにもなります。
現代の若者は、抽象的な表現や回りくどい言い方に対して距離を感じることが多く、シンプルで率直な言葉を好みます。そのため、やさしい日本語の12のルールを応用して話しかけたり、業務指示や評価を伝えることで、信頼関係を築きやすくなります。
また、彼らは多様性を尊重する価値観を持ち、自分自身も「理解されたい」「受け入れられたい」という想いを強く持っています。つまり、言葉の配慮=人間関係の配慮として受け取られやすく、エンゲージメントの向上にもつながります。

Z世代の心をつかむやさしさのある伝え方
以下に、Z世代への対応に役立つ「やさしい言葉がけ」の実例を紹介します。
◇指示を出すとき
- ✕ それは臨機応変に対応しておいて
- 〇 わからないときは、すぐ きいてください。いっしょに かんがえます。
◇フィードバックをするとき
- ✕ この点は再考してほしい
- 〇 ここは ちょっと ちがいます。いっしょに なおしましょう。
◇モチベーションを高めるとき
- ✕ 君の努力は評価しているよ
- 〇 がんばってるね! いつも みてます。
◇面談やキャリア相談
- ✕ 今後の方向性を自主的に決定してください
- 〇 これから どう したいか いっしょに かんがえましょう。
これらの表現は、やさしい日本語の基本ルールに沿いながらも、丁寧さと誠実さを伝えることができます。言葉の温度を下げずに、わかりやすさを高める。これこそが、Z世代の定着に向けた新しい言語戦略といえるでしょう。
やさしい日本語はすべての人のためのコミュニケーションツール
「やさしい日本語の12のルール」は、日本語に不慣れな外国人のための言葉の工夫として始まりました。しかし今では、Z世代の若手社員や多様な働き手が集う現代の職場においても、大きな意味を持つ普遍的なコミュニケーション手段となりつつあります。
この記事で紹介したように、簡単な言葉・短い文・分かち書きなどの工夫を取り入れることで、誤解を防ぎ、信頼を育てることができます。また、社内文書や採用サイトなどの情報発信においても好印象を与えられるのは大きなメリットです。
「やさしい日本語」は、外国人だけのものではありません。むしろ、日本語話者全員が使うことで、より良い関係性が築けるものです。誰もが「わかる」「伝わる」「受け入れられる」環境づくりの第一歩として、職場の中に“やさしい言葉”を取り入れることが、いま求められています。
FAQs
やさしい日本語のルールは外国人住民だけに必要ですか?
いいえ。やさしい日本語は外国人住民だけでなく、Z世代や高齢者、日本語が苦手な日本人にも有効です。誰にでも伝わる言葉づかいが大切です。
分かち書きとは具体的にどのようなものですか?
分かち書きとは、単語ごとにスペースを入れる方法です。例:「かいぎ は 3がつ 5にち に あります」。視認性が高まり、情報伝達がよりスムーズになります。
やさしい日本語は正式な情報発信にも使えるのでしょうか?
はい。2020年の災害情報やコロナ関連情報の際にも、やさしい日本語での掲載・発信が多数行われました。正確で伝わる表現は、緊急時にも役立ちます。
自治体以外の組織でもやさしい日本語を活用できますか?
「はい。自治体だけでなく企業、病院、学校などあらゆる場所で活用可能です。社内文書や採用ページなどでも効果があります。
掲載する文書に漢字を使う場合の注意点は?
漢字の使用量に注意し、難しい言葉は避けて、ふりがなを付けるか、簡単な語彙に置き換えるようにしましょう。読み手の理解度が大きく向上します。